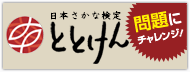- ホーム >
- 魚食にっぽん >
- ととけんの問題にチャレンジ! >
- 【ととけん】2017年7月問題
【ととけん】2017年7月問題
Q1.日差しが強くなって麦わら帽子をかぶりだす夏に旬をむかえるこの魚介は、“麦わら”と呼ばれています。関西では半夏生に食べる風習がある、下線部に入るこの魚介を選びなさい。
[2016年(第7回)3級(初級)から出題]
[2016年(第7回)3級(初級)から出題]
?アワビ
?サザエ
?タコ
?タラ
?サザエ
?タコ
?タラ
A.答えを見る
Q2..こんがり焼いた身に醤油をさした時のジュッという音がたまらないサンマ。7月になるとある港の“サンマ初出荷”というニュースが流れ、いよいよサンマシーズンの幕開けとなります。この漁港を選びなさい。[2010年(第1回)2級(中級)から出題]
?根室
?気仙沼
?女川
?銚子
?
?
?銚子
A.答えを見る
Q3.細長い棒状の魚体の3分の1はあろうかという長いくちばしを持つ個性的な姿の魚。身肉部分が少なくコストパフォーマンスはいまひとつともいえますが、極上の味を持ち希少なことから料理人の憧れの的。夏に旬を迎えるこの魚を選びなさい。[2014年(第5回)1級(上級)から出題]
?サヨリ
?アカヤガラ
?ダツ
?ギンポ
?アカヤガラ
?ダツ
?ギンポ
A.答えを見る
BACK NUMBER
- Vol.161 次世代へつなぐ「鰻愛」
- Vol.160 「魚がうまそう!」 SNSで産地を伝える
- Vol.159 サーモンのラーメンはいかが
- Vol.158 減塩課題 技術でサポート
- Vol.157 国内外から注目の「おにぎり」
- Vol.156 今年のバレンタインは魚で!
- Vol.155 家族で作る、おせち料理
- Vol.154 バーガーで食べるシーフード
- Vol.153 進化した冷凍技術で「へい!お待ち。」
- Vol.152 街の魚屋さんに教わる 離乳食と魚
- Vol.151 魚に触れる機会つくる
- Vol.150 湖魚を深堀り
- Vol.149 海業振興にBBQの提案
- Vol.148 伝えたい 漁師のリアル
- Vol.147 サーモンはなぜ日本人に愛されるのか
- Vol.146 豊洲市場の広報戦略
- Vol.145 その水産物もアップサイクル!
- Vol.144 魚がもっと食べたくなる、特化型本屋
- Vol.143 やっかい魚缶詰の全国大会
- Vol.142 毎月3–7日は「さかなの日」
- Vol.141 ラジオで聞く魚食
- Vol.140 海洋大で人気「魚食文化論」
- Vol.139 魚食の新星!水産インフルエンサー
- Vol.138 広がるオルタナティブフード
- Vol.137 キャッチ&おいしくイート
- Vol.136 一流の味をタクシーで運ぶ「うなタク」
- Vol.135 アサリから考える評価基準
- Vol.134 魚のヒレに魅せられて
- Vol.133 急拡大する「日本のノンアル文化」
- Vol.132 ゲノム編集魚で広がる可能性
- Vol.131 イカがもっと好きになる
- Vol.130 魚の価値、正しく伝えたい
- Vol.129 対馬の「ユーチューバー」
- Vol.128 調味ソースで魚食盛り上げにひと役!
- Vol.127 魚肉タンパクが熱い
- Vol.126 定番化する手巻き寿司
- Vol.125 CFで聞いてみたい、当社の新作に興味ある?
- Vol.124 人気のアニメとコラボ 売場活性化や価値訴求に
- Vol.123 Sea級グルメで売り込め!港町のご当地味自慢
- Vol.122 豊洲仲卸が移動販売に挑戦、亀和商店
- Vol.121 広がる冷凍販売
- Vol.120 魚はもっと語ることがある/ととけん
- Vol.119 今年の冬は「こなべ」
- Vol.118 魚の絵 地域振興
- Vol.117 コロナ禍での魚食普及・オンライン祭り現場に潜入
- Vol.116 安心して楽しむ「おせち」
- Vol.115 魚があれば楽しめる!スポーツ観戦と家飲み
- Vol.114 活況のいなせり市場(豊洲仲卸・消費者向けEC)
- Vol.113 うちで捌こう♪ステイホームで変化
- Vol.112 訪ねよう街の魚屋
- Vol.111 海藻食べて健康に
- Vol.110 アウトドアで楽しむ「国分」缶つま10周年
- Vol.109 ニタリクジラを食べる
- Vol.108 サバ缶ブームの次はイワシ缶
- Vol.107 魚にプラス、醤油の力再発見
- Vol.106 野菜とコラボで“洋風”魚惣菜
- Vol.105 スケソウ食べて筋力アップ
- Vol.104 消費増税追い風にテークアウトで魚食開拓へ
- Vol.103 食の革命なるか?スシ・シンギュラリティ
- Vol.102 クジラ、サンマで令和新食材
- Vol.101 ひろがる「ホヤ食」
- Vol.100 あの手この手で魚食提案「100号記念」本紙記者座談会
- Vol.99 「令和」を大歓鯨!めで鯛時代に!!
- Vol.98 釣った魚が街中で使えるクーポンに!「 ツッテ熱海」
- Vol.97 外食業界初 うま味たっぷり干物鍋
- Vol.96 サバ食ブームはなぜ起きた?
- Vol.95 カツオ節で満ちる幸福
- Vol.94 魚を食べるきっかけづくりを
- Vol.93 豊洲市場の魚食発信
- Vol.92 よりおいしくなった!? ホンビノス
- Vol.91 「日本一魚をさばける」料理教室
- Vol.90 未来の食シーンが変わる?「すしテレポーション」注目
- Vol.89 冷凍専門! クールな魚屋
- Vol.88 「…けれど」を取り除く。オイシックスドット大地
- Vol.87 日本初、池袋に「くさやバー」
- Vol.86 ぐるなび外国語版でメニュー紹介
- Vol.85 検証・底引き混獲魚は宝の山
- Vol.84 「築地ワンダーランド」受賞、核心に食育
- Vol.83 佐賀県産品「あさご藩」プロジェクト
- Vol.82 芸は魚(うお)助ける、鹿屋市お笑い活用
- Vol.81 熟成魚、福井・美浜の味再現
- Vol.80 神戸市場本場 「魚河岸デー」で 魚食復興へ!
- Vol.79 見ているだけで楽しい1分動画レシピ
- Vol.78 獲れたて魚を対面直売、うみてらす豊前
- Vol.77 大水槽の前に 寿司処?資源安定の魚種のみ寿司種に
- Vol.76 魚食推進に戦隊キャラが活躍
- Vol.75 お魚ふりかけを、成長産業に
- Vol.74 「丸魚しか売りません!」おかしらや旗の台店の挑戦
- Vol.73 魚は〆て何日後がおいしいか
- Vol.72 熱戦!全国学校給食甲子園
- Vol.71 若い主婦層に自宅おせちの勧め
- Vol.70 「落語で食育」にヒントあり
- Vol.69 時代は“さばける男子”
- Vol.68 横浜市場の開放行事楽しもう
- Vol.67 栄養とって強くなれ!食とスポーツ
- Vol.66 夏のスタミナ・疲労対策に土用のシジミ
- Vol.65 今年は鯨肉で夏バテ知らず!
- Vol.64 10年目のお魚マイスター
- Vol.63 魚で外からもキレイに
- Vol.62 産地を意識して“ノリ”を選ぼう
- Vol.61 気仙沼の魚を学校給食に普及させる会
- Vol.60 ヒロ中田さん、「新・ご当地グルメ」提唱
- Vol.59 「ガストロ」という魚をご存知ですか
- Vol.58 舩久保正明・五ツ星お米マイスターに魚食普及のヒントを聞く
- Vol.57 うまさ飲み干す、ヒレ酒・骨酒
- Vol.56 制定から10度目の「魚の日」目利きの関心、魚食につなぐ
- Vol.55 「いつでも生サバ」蓄養物を〆た当日に
- Vol.54 “出来たて”より美味い「水産缶詰」
- Vol.53 乾物は万能食品、実は売場のキーワード
- Vol.52 その塩分大丈夫? 食品業界では減塩の動き
- Vol.51 健康・美容にナマコ
- Vol.50 めでタイを復活させタイ
- Vol.49 今、魚用調味料が熱い! 主婦の悩みを解消
- Vol.48 おいしさを数値化/選択しやすく、売り上げ伸ばす
- Vol.47 魚の個性を大事に?鈴木香里武・フィッシュヒーラー
- Vol.46 お魚を野菜と一緒においしく
- Vol.45 ライブ感で増幅、目・耳・鼻で味わう魚
- Vol.44 進化する「活〆」
- Vol.43 サメとエイ、美味しく新しい水産食材
- Vol.42 外食チェーン、おいしさ求め国産魚に熱い視線
- Vol.41 KIRIMIちゃん./魚食普及に救世主か
- Vol.40 河岸へ行こう!/市場訪問のすゝめ
- Vol.39 その“旬”は本物?/春カキで実証
- Vol.38 鮮魚流通の「Amazon.com」へ、IT技術で24時間体制の受注
- Vol.37 完全ご飯給食?南房総市の学校で魚献立は?
- Vol.36 丸魚が売れるスーパー/魚好きが満足する店を目指し
- Vol.35 高校生の「魚はこう食べたい」/i.club気仙沼プロジェクト
- Vol.34 魚肉パワー/日本人には魚がいちばん
- Vol.33 「湯煮」ってナニ?/魚の理想的な調理法
- Vol.32 魚食を未来に/水産高校生の柔軟な発想
- Vol.31 富山独自のコンブ文化、魚食を増やすヒント
- Vol.30 「ハラル認証」取得で、イスラム圏に日本の魚食を売り込め
- Vol.29 アレルゲンフリーで魚食
- Vol.28 宅配寿司/“未利用魚”を積極活用
- Vol.27 大型連休、家族揃って水族館
- Vol.26 脱・観光市場のススメ
- Vol.25 猫は日本の魚食文化の脇固める?!
- Vol.24 受験生応援/魚で縁起担ぎと身体づくり
- Vol.23 凍ったままで料理できる。それって常識?
- Vol.22 スローに楽しく♪福探し「鯛の9つ道具」
- Vol.21 解凍で変わる!冷凍素材を生かす
- Vol.20 素材に眠る力、小小カズノコの消費拡大へ
- Vol.19 色で魅せる、味のイメージ喚起
- Vol.18 【栄養価はウナギに匹敵】夏バテにドジョウ
- Vol.17 【地方発・米と魚の新ビジネス】米粉パンに挟む、乗せる
- Vol.16 魚のDHA/EPA、機能性が最高評価
- Vol.15 “内地”に海産魚を売り込め
- Vol.14 ニーズの“すれ違い”なくせ!!/鮮魚のあるべき売り方
- Vol.13 平日の「おひとりさま」魚食戦線
- Vol.12 受験シーズンに「魚で勝つ!!」
- Vol.11 魚食にっぽん/来年も引き続き情報発信へ
- Vol.10 全国公募の“もえ”キャラが営業「静岡もえしょくプロジェクト」
- Vol.9 電子レンジで簡単に加熱調理、包材メーカーの技術開発
- Vol.8 産地=消費地・流通がつなぐ/「生鮮時間便」・「ふるさと小包」
- Vol.7 米国の魚食事情/米国内消費は伸びる傾向
- Vol.6 サンマ全国でなぜ売れる 消費減少からの回復/生鮮の牽引、西日本で急増
- Vol.5 天然の“ダシ”楽しめるスポット、幅広い年齢層が注目
- Vol.4 宅配ビジネスどうやって“売る”か
- Vol.3 鮮魚を売る底力/鮮魚専売上トップの高山信行・北辰水産専務
- Vol.2 美容は“魚”で/座談会・ウギャルx築地ガールズ
- Vol.1 学校給食の水産物利用の現状/村上陽子 教授